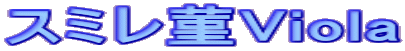
「山路来て なにやらゆかし すみれ草」(芭蕉)
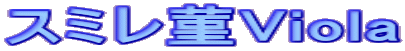
「山路来て なにやらゆかし すみれ草」(芭蕉)
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
| 神戸・六甲山のスミレ ◎六甲山系でよく見かける(R)神戸市レッドデータ | ||||
| △アオイスミレ | 有茎種。花期が早い。花後匍匐枝を伸ばし栄養繁殖する。葉は円心形。六甲山では少ない。全体に毛がある。識別ポイント:①マルバスミレとは葉の形がよく似るが、花期の葉の先が少し尖り、夏葉は円くなるのが特徴。マルバスミレは逆。②タチツボスミレとは毛の有無で見分ける。果実は円く、葉より下で熟す。 | 白~淡赤紫上弁がウサギの耳。距は上に立ち上がる。 | 円形。花の咲き始めは丸まっている。葉は白い毛が多い。葉は花が咲き終わった後、大きくなる。 | |
| (C)アカネスミレ | 神戸市R(C)群落のそばに近寄るとほのかに香る。一株あたりの花の数が多く、小群落となったものは見応えがあり美しい。植物全体に白い短い毛が密生。丘陵に多い。 | 濃い紅紫色 | 卵形で基部はややハート型。 | |
| アギスミレ | ニョイスミレの変種。花期の葉は基部の湾入が目立たないが、夏葉はブーメラン型。六甲山系では沢筋で見られる。アギは顎(あご)の訛化。葉の基部が左右に張り出すことによる。 |
白色。唇弁に青色の筋が入る。 | ブーメラン状 | |
| ◎アリアケスミレ | 市街地でも。白色の花弁に赤紫色の筋が入るものが標準的。花期には葉が内側に巻いている。山麓から中腹までよく見られる。葉の数が多い。花の色の変化の多さを有明の空に見立てた名前。全体無毛。 | 白色・淡紫・濃紫と変化多い。距は太くやや短い。 | 葉は3~10枚。披針形で幅が先端までほぼ一定、先は鈍頭。葉柄に翼。花期の葉は葉柄より葉身の方が長く、花後は逆になる。 | |
| (C)ウスアカネスミレ | 神戸市R(C) アカネスミレの品種。植物全体に毛。 |
アカネスミレの赤紫色に対し淡紫色。距はほそながくい。 | ||
| (C)エイザンスミレ | 葉が深裂。花は淡紅色~白色と多様。花直径2~2.5。花弁の縁が波状。神戸市R(C)比叡山に生えるスミレの意味。香りが良い。ヒゴスミレとは葉の裂片の幅が広いこと、花弁が波打つことで区別。 | 白から濃いピンク。花弁の縁が波打つ。 | 葉は3全裂するものや鳥足状に5全裂するものあり。夏葉は極端に大きくなるものが多い。 | |
| オトメスミレ | タチツボスミレの品種。 | 花弁は白で距だけが紅紫色。 | ハート型。托葉に櫛の歯状の切れ込み。 | |
| △コスミレ | 条件によっては1株で20個以上花を付ける。花は淡紫色のものが多いが、濃淡は株により多様。花弁は細く側弁が基部から完全に開くため柱頭がよく見える。山麓から中腹まで見られるが数は少ない。花弁はほっそり。Viora japonica 種小名に日本名を持つ唯一のスミレ。六甲山系では山麓から中腹まで見られるが数は多くない。 | 上弁が兎の耳のように立ち上がる。淡紫~少し濃いめの紫色。花を正面から見ると、雌しべや雄しべの付属帯がはっきり見える。萼片に付属帯がある。 | 卵形で先は尖る。最後に夏葉は三角形。しばしば葉裏は紫色を帯びる。スミレ・アリアケスミレに比べ葉の幅が広い。 | |
| コタチツボスミレ | 六甲山系では裏六甲、最高峰付近に多い。タチツボスミレの変種。タチツボスミレに比べ深いハート形にならない。葉の鋸歯が粗い、などの特徴有り。 | 淡紫色 | 三角形から腎形。 | |
| ◎シハイスミレ | 六甲山を代表するスミレの一つ。葉を斜上させる。葉表面は濃緑色で光沢。裏面は紫色を帯びる。林縁など不通に見られる。花付きが良く、数株がかたまった場所では豪華。植物全体無毛。 | 濃紅紫~淡紅紫まで変化が多い。。側弁基部無毛。雌しべがよく見える。 | 葉は地面にほぼ水平から少し上向きで展開。三角形で基部は深いハート型。縁に低い鋸歯。裏面は紫色を帯びるものが多い。 | |
| シロバナナガバノタチツボスミレ | ナガバノタチツボスミレの品種。 | 白色。唇弁に紫色の筋が入る。距は紫色を帯びる。 | ナガバノタチツボスミレと同様に葉脈に赤紫色の筋が入る。 | |
| ◎スミレ | 市街地でもよく見かける。葉はへら型で葉柄に翼がある。花は濃紫色。山麓から中腹まで見られる。 スミレ全体をいう場合と区別するため学名のマンジュリカの名で呼ぶ場合も。(満州産のの意味)。根は茶色でやや太い。 |
花は葉よりも上で咲く。(アリアケスミレとの区別ポイント)濃紫色が多いが、淡いものなど変化に富む。 | 葉柄に明らかな翼があり、葉身より長いかほぼ同じ。濃い緑色。披針方。葉の毛がビロード状。 | |
| ◎タチツボスミレ | 六甲山系では山麓から最高峰まで不通に見られる。花の後、地上茎を伸ばす。(アカフチタチツボスミレは葉に赤い斑。最高峰裏六甲には(コタチツボスミレ) | 淡紫。花の中心部の白い部分がはっきりしない。 | ハート型。托葉に櫛の歯状の切れ込み。 | |
| ツボスミレ(ニョイスミレ) | 有茎種レ。湿った道端、林縁に。別名ニョイスミレ。ツボスミレは庭に咲くスミレの意味。 | 白色。大きさはタチツボスミレの半分大。 | 葉はハート型で低い鋸歯。基部は広く湾入し。長さより横幅の方が大きい。 |
|
| ◎ナガバノタチツボスミレ | 六甲山で最も多いスミレ。花期の終わりに花茎を伸ばし立ち上がる。類似種のタチツボスミレより炊く托葉の切れ込みが鋭い、やや粗い。 | 淡紫。稀に紫 | 茎葉は長三角形状楕円形。根生葉は円心形。光沢があり、葉脈が赤くなるものも多い。 | |
| ニオイスミレ | 花に強い香り。香水の原料。スミレの花束にも。ナポレオンの愛したスミレ。耐寒性が高く、1月から咲き始める。在来のアオイスミレの近縁種。 | 濃青紫色。淡色の品種も。直径1.8mm。 | 円形。花の咲き始めは丸まっている。葉は白い毛が多い。葉は花が咲き終わった後、大きくなる。 | |
| ニオイタチツボスミレ | 中腹以上の所々で見られる。 花柄にビロード状の毛があるのが顕著な特徴。 |
濃紫~淡紫。花の中心部が白く抜ける。 | 根生葉は円形ハート形。先は鈍頭。基部はハート型。葉の色は鮮緑色。葉柄や葉の両面に毛。 | |
| ◎ニョイスミレ(ツボスミレ) | →ツボスミレ 葉の形が仏具の如意に似るため。開花がスミレの仲間で最も遅い。花茎を斜上させる。 |
白色。大きさはタチツボスミレの半分大。白色で小さい。唇弁に青い筋。 | 葉はハート型で低い鋸歯。基部は広く湾入し。長さより横幅の方が大きい。 | |
| ノジスミレ | スミレに似るが、花期が2週間早い。ほとんど翼が無い。識別ポイント:①スミレの花の色は青みがからない紫で、中心部の白色が目立たず、側弁基部は有毛。葉柄の翼は明瞭。②コスミレの花は淡紫色、葉の両面無毛。 | 青みがかった紫色で中心部が白く抜ける。距は細長い。 | 披針形で先が尖り、両面にビロード状の短い白毛が生え、葉柄基部には多い。 | |
| ハグロシハイスミレ | 近畿地方に多い。シハイスミレの一種。 | 普通のシハイスミレより濃いものが多い。 | 表面が黒紫色~暗紫色を帯びる。葉の表面には光沢あり。 | |
| (C)ヒゴスミレ | 葉が深裂。花は白色。神戸市R(C)。香りがある。園芸種のヒゴスミレは中国産、野生のヒゴスミレは低地では育たない。 | 白色。ときに淡紅色。 | 葉は5全裂し、各裂片はさらに細かく切れ込む。 | |
| ヒナスミレ | 山麓で見られるが数は少ない。葉柄に翼無し。葉縁に鋸歯。 | 花弁は波打ち、淡い紅紫色。 | 葉も展開しはじめは縁が波打つ。地面に対し水平に広がる。ハート型。鋸歯は目立つ。先は尖り基部は深く湾入する。両端はほとんど接しない。 | |
| △ヒメスミレ | 人の手の加わった所に生える(ゴルフ場・グランド・花壇・盆栽鉢)。識別ポイント:①花がスミレやノジスミレより遙かに小さいので区別は容易。②夏葉でもノジスミレやアリアケスミレのように立ち上がらず縁は波打つかんじ。六甲山系では山麓で見られるが数は少ない。 | 花は小さく上弁が兎の耳のように立ち上がる。濃青紫色。紫条が目立つ。距は花が小さい割りに太く、白から淡褐色。 | 披針形であるが、夏はになると長くなるものが多い。裏面は淡緑色であるが紫色を帯びるものも。縁に細かい鋸歯。波打つ傾向。翼はほとんど無い。 | |
| ヒメアギスミレ | ニョイスミレの変種。アギスミレよりも小型で、葉が極端にブーメラン形になるものをいう。アギスミレ同様、花期より花後のほうがブーメラン形となる。アギスミレの約半分大。 | 白花に紫の線。 | ブーメラン形。 | |
| ヒラツカスミレ | ヒゴスミレとエイザンスミレの自然交配種。ヒゴとエイザンの混生する場所で発生する。(神奈川県平塚市の望月氏がヒゴスミレとエイザンスミレの人工交配種を作ったため) | 白~淡紅紫色と幅広い。側弁の中心部はヒゴスミレのように黄色を帯びる個体が多い。 | 3裂もしくは5裂。5裂の葉はヒゴスミレより裂片の幅が広い。 | |
| フイリフモトスミレ | フモトスミレの一種。地味だが気品がある。山麓に生えることが多いので名がついたが、1000m以上の山地でも見られる。 | 白色で唇弁に赤紫色の筋が入る。側弁は下を向く。 | 葉は根生し、葉を水平に開く。葉身は卵形だが、株により多様。光沢はなく、表面に白色の斑が入る。裏面は赤紫色。 | |
| フイリヒナスミレ | ヒナスミレの斑入り品種。普通のヒナスミレより優雅な感じがする。 | 花の直径1.5~2cm。ヒナスミレと同様に側弁の基部に毛が生える。 | 葉を水平に広げるのもヒナスミレと同様。 | |
| ○フイリシハイスミレ | 比較的よく見かける。葉の表面の葉脈に沿って白色の斑が入るシハイスミレの一品種。 | |||
| ホコバスミレ | スミレより全体に細め。花数少ない。スミレの変種。 | スミレに比べ、立ち上げる花茎の数は少なく、花弁が細い。 | 本種の葉身は鉾形(長楕円状披針形)で、葉柄に翼がある、母種のスミレに比べ葉身が細い。 | |
| マキノスミレ | シハイスミレの変種。無茎種でシハイスミレに比べ、葉がほぼ垂直に立ち上がり、葉が細いなどの特徴。マキノスミレの分布の西限が六甲山付近となるため、シハイスミレとマキノスミレの中間的なものが見られる。葉が立ち上がり、葉身の幅が広いタイプが多い。東日本に多いスミレ。シハイスミレとの混生ちいきでは区別が難しい。葉の数、花の数とも少ない。 | 濃紫色のものが多く、葉より下で咲くものが大半。 | ||
![]()
| アリアケスミレ | スミレ | ||
 |
 |
 |
 |
| 葉は3~10枚。披針形で幅が先端までほぼ一定、先は鈍頭。葉柄に翼。花期の葉は葉柄より葉身の方が長く、花後は逆になる。 | 白色の花弁に赤紫色の筋が入るものが標準的。 | 葉柄に明らかな翼があり、葉身より長いかほぼ同じ。濃い緑色。披針形。葉の毛がビロード状。 | 花は葉よりも上で咲く。(アリアケスミレとの区別ポイント)濃紫色が多いが、淡いものなど変化に富む。 |
| 識別ポイント | 識別ポイント | ||
| ①シロスミレに似るが、生える場所が低地で(人家周辺・田んぼ・川原の土手・植え込み・線路沿いなどの少し湿った場所)花期の葉の葉柄が葉身より短く、葉の数が多い。 ②スミレとは、花の色で見分ける。濃紫色のものも紫条が目立つ。 花色の変化と有明の空に因んで名付けられた。 |
①アリアケスミレとは距が長いこと、花が葉よりも高く咲くことで区別。 ②ノジスミレは花に青みがあり、側弁基部は無毛で、葉の毛がビロード状、葉の翼が狭い。 濃紫色の花をつける代表的なスミレ |
||
| タチツボスミレ | ナガバノタチツボスミレ | ||
 |
 |
 |
 |
| ハート型。 | 淡紫。花の中心部の白い部分がはっきりしない。 | 茎葉は長三角形状楕円形。根生葉は円心形。光沢があり、葉脈が赤くなるものも多い。 | 淡紫。稀に紫 |
| 識別ポイント | 識別ポイント | ||
| ①ミヤマスミレ類とは地上茎があり、托葉が櫛状に切れ込み、柱頭が棒状で単純な点で区別。 ②関東地方では、淡紫色のスミレで托葉が切れ込んでいればほぼ本種。 全国で日本の春を告げる身近なスミレ |
①ニオイタチツボスミレの花柄にはビロード状の毛があり、花の中心部が白く抜ける。また葉の色は明るい緑色。 ②タチスミレとは、生育場所、花、葉の色で区別。 茎につく葉が細長い、西日本を代表するスミレ |
||
| シハイスミレ | ニョイスミレ(ツボスミレ) | ||
 |
.jpg) |
 |
 |
| 葉は地面にほぼ水平から少し上向きで展開。三角形で基部は深いハート型。縁に低い鋸歯。裏面は紫色を帯びるものが多い | 濃紅紫~淡紅紫まで変化が多い。。側弁基部無毛。雌しべがよく見える。 | 葉はハート型で低い鋸歯。基部は広く湾入し。長さより横幅の方が大きい。 | 白色。大きさはタチツボスミレの半分大。白色で小さい。唇弁に青い筋 |
| 識別ポイント | 識別ポイント | ||
| ①マキノスミレの葉はほぼ垂直に立ち、披針形で幅は狭く、花は葉より下で咲き、濃紫色。 ②フモトスミレは花が白色で小さく、葉は小型で広卵形。 西日本の山地や丘陵を鮮やかに彩る。 |
①アギスミレは葉がブーメラン状になる。 ②タチツボスミレと比べ花は白色で約半分大、花期は半月ほど遅い。葉は淡い緑色、托葉は櫛の歯状に裂けない。地上茎有り。本州で普通に見られる花の小さなスミレといえばこれ。 |
||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |